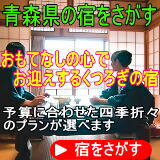 |
青森県 「日本中央の碑」日本中央の碑は1949年(昭和24年)に偶然発掘されましたもので、石には日本中央と刻まれていたことから言い伝えに残る「壺の碑(つぼのいしぶみ)」ではないかと論議をかもした碑です。 壺の碑とは坂上田村麻呂が蝦夷地征伐した際に「日本中央」の4文字を刻んだ石碑といわれ、以来多くの人が探し求めるが見つからず、探し求めても手に入らないもの、遥か遠くの物の象徴として、西行法師や源頼朝、和泉式部などが和歌にも詠んでいます。義経北行伝説では義経はこの「壺の碑」に立ち寄ったとされ、事実なら鎌倉時代前期はまだ街道筋に存在していたとも考えられますが、いつしか所在が不明となり明治天皇などは東北巡幸の際には壺の碑伝説が伝わる千曳神社にお立ち寄りになり「壺の碑」を捜索させたと云われています。 東北町で見つかった碑はまさに「日本中央」の4文字が刻まれており、言い伝えに残る「壺の碑」ではないかと論議をよんでいますが、未だはっきりとしたことは分かっていません。 なお碑に刻まれている「日本」とは平安の当時は中央政府の手が及ばない東北地方を意味し、現代風に訳すと「東北の中央」となります。 |
| 日本中央の碑歴史公園 ・所在地:青森県上北郡東北町字家ノ下タ39番地の5、39番地の6 ・開館時間:9時〜16時 ・休館日:毎週火曜日・年末年始12月28日から翌年1月4日まで ・駐車場:あり20台(無料) ・入場料:無料 |
|
青森県の東北町にある日本中央の碑。展示館は国道4号線沿いにあり、何気なく入ってみたら平安時代から現在に至るまで多くの人が探し求めた碑である可能性が高いミステリアスなものであることが分かり少々驚いてしまった
日本中央の碑が展示されている展示室。以前は小さな祠に石碑が納められていたのだが平成7年に立派な展示室が作られた。室内には日本中央の碑の他、古代東北の資料が展示されている。
日本中央の碑歴史資料館。国道4号線沿いにあり、青森市方面から来る場合、みちのく有料道路の入り口手前にある。なにも知らない人が青森県の片田舎で「日本中央の碑」という看板を見ると驚いてしまう。
青森県内にある神社の中ではもっとも古いと言われている千曳神社。一昔前までは「天魔林」と呼ばれた森の中にたたずんでいる。日本中央の碑は千曳神社のすぐ近くで見つかっており、この両者はなんらかの関係があるものと推測されている。
日本中央の碑が発見された千曳神社は七戸町菩堤木にある神社で坂上田村麻呂の建立と伝えられています。祭神は八衢比古(やちまたひこ)と八衢比売(やちまたひめ)の夫婦神。外部から侵入する悪いものを防ぐ神様で家内安全や旅の安全祈願などのご利益があるとされています。
千人で引っ張っても動かない石の精を村娘のつぼ子が一人で運んだという言い伝えが残され、これが「千曳」という名前の由来になっています。また明治天皇が御旅行の際に訪れたこともありなにかと逸話の多い神社です。
このほか坂上田村麻呂や千人で引っ張っても動かない石の精、それと引っ張った娘の名前「つぼ子」など日本中央の碑(つぼのいしぶみ)に通じる言い伝えが残されていることから「日本中央の碑」となんらかの関係があるのではないかと推測する研究家もおおい神社です。
| 日本中央の碑周辺のおすすめスポット一覧 | ||||||
 |
青森県の観光地・宿 |  |
||||
| 青森市 | 夏泊半島 | 下北半島 | 野辺地町 | 七戸町 天王神社 | ||
| 小川原湖 | ||||||