| 日本の観光地・宿>東北の観光地・宿>岩手県の観光地・宿>御所野遺跡 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 御所野遺跡の竪穴式住居 御所野遺跡の竪穴式住居。御所野遺跡では800を越える住居跡が見つかっていますが、特徴的なのは土屋根であること。これは消失家屋跡の調査の結果判明したもの。 |
こちらは竪穴式住居内で火を焚いている光景。ボランティアの方が復元された住居ひとつひとつをまわって中央の炉で火を焚いていた(虫除けや乾燥の為)。なお煙の臭いが結構きついので、気になる方は火を焚いた直後住居内に入るのを控えた方がよいかもしれない。 |
|||||||||||||||||||
| 竪穴式住居の内部 御所野遺跡の竪穴式住居内部。地面を一段深く掘り下げ中央で火を焚くスタイルは日本で見られる竪穴式住居共通の特徴。だだし御所野遺跡の屋根は他とは違い土で作られていたと考えられている。 |
御所野遺跡の堀立柱建物 御所野遺跡の堀立柱建物。主に倉庫として使われネズミや害虫の被害から守る為に柱を立てて高床式にしたと考えられる。写真の建物は小さめだが、他にもっと大規模な建物が建てられていたと言われている。 |
|||||||||||||||||||
| 御所野縄文遺跡の特徴 御所野縄文遺跡は縄文前期から中期にかけて北海道南部から東北地方にかけて分布していた円筒土器文化圏に属しており、三内丸山遺跡やストーンサークルで有名な大湯環状列石とほぼ同時代・同文化圏の遺跡。 御所野縄文遺跡の特徴としては住居の屋根や壁が土で覆われていたことと意図的に燃やされた住居跡があること、そして死者の埋葬場所と想定される配石遺構を中心に集落が形成されていることがあげられる。 また遺跡がある場所は東京から青森を結ぶ国道4号線でももっとも標高が高い地域に形成されているが、当時は地球の温暖化が進み獣類やクリ、ドングリ、アケビなどが豊富に採れ、集落の生活を支えていたと考えられている。 また津軽海峡をこえた北海道や新潟地方との交流の跡も確認され広範囲にわたって他の地域と交流があったと考えられている。 縄文時代の住居 縄文時代の住居は倉庫や村の長老、シャーマンなど特殊な機能、人物の建物以外は竪穴式住居だったと考えられています。竪穴式住居とは簡単に言えば地面に竪穴を掘ったものです。しかし縄文人達は本当にこんな住居で生活していたのでしょうか?実はあるボランティアの方が復元住居で実際に生活してみたそうです。まず水ですが大雨の日でも住居内に雨水が流れ込んできたり、湧き出てくるようなことはなく、また内部は地面を掘り下げている為、夏はヒンヤリ涼しく、冬は暖かく感じたそうです。縄文時代は現在より気候が温暖だったと考えられており竪穴式住居でも人々は冬の寒さを十分しのげたのではないかと推測されています。 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
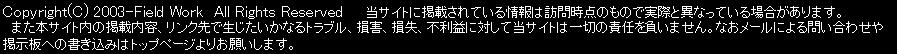 |
||||||||||||||||||||


