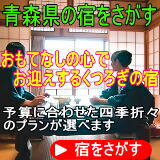 |
青森市 「あおもりねぶた祭り」青森ねぶた祭りは青森市中心部で行われる夏祭りで青森県内で行われるねぶた祭の中では人出、規模共に最大のお祭り。まつりの起源として一般的にいわれているのは坂上田村麻呂が陸奥国の蝦夷征討の戦場において敵を油断させておびき寄せるために大燈籠・笛・太鼓ではやし立てたことといわれているが他にも諸説ありはっきりとは分かっていないそうです。 ねぶた開催期間中は市内に交通規制がかかり激しい交通渋滞が発生します。この為、確実にねぶた祭を楽しみたいという方は早い時間に訪れ駐車場を確保しておくか、宿を取っておく方が無難。また可能なら観覧席も予約しておくとよいでしょう。なお青森県内では同時期に各所でねぶた祭が開催される(弘前ねぷた、黒石ねぶた、五所川原立佞武多)ので、ねぶた祭ツアーを企画する観光客や旅行会社も多いそうです。 |
青森ねぶた祭り。毎年8月2日から7日まで開催される東北地方最大の夏祭り。毎年300万人以上が訪れる。夜は会場運行と共に陸奥湾に花火が打ち上げられ夏の夜空を彩る。
青森ねぶたを彩る「ハネト」。ハネトは衣装さえ着れば自由参加となっており、衣装は地元のデパートや衣料店で販売、貸出をしてくれる。なお私はハネトに参加したことはないが、その名のとおり跳ねながらすすむので足を怪我することもあるので注意が必要。

青森市のメインストリート。国道4号線及び7号線を運行するねぶた。片側4車線もある国道もねぶた祭りの日は通行止めとなり祭り一色になる。

青森市街地を運行するねぶた。ねぶたは花形の「大型ねぶた」や「子供ねぶた」など総勢35台ほどが出陣し約一週間にわたってみちのくの夜を彩る。祭り最終日の「ねぶたの海上運行」は幻想的で見応えがある。

東北地方には坂上田村麻呂の言い伝えが実に数多く残されています。田村麻呂は松島の五大堂や平泉の達谷窟、青森県では深浦町の円覚寺などといった有名な寺社の創建時の由来に登場していまし、鯛島や八幡平のように田村麿が登場する言い伝えが残る場所も多数あります。そしてこれらの伝説の極めつけが青森県の「ねぶたまつり」です。
そもそも史実では田村麻呂は宮城県と岩手県の県境付近までしか来ておらず、青森県には足を踏み入れていないとされています。また東北の人々からすれば田村麻呂は征服者の大将であって、どちらかと言えば忌み嫌われる立場の人間のはずですが、言い伝えではどれも田村麿を神格化して描いています。これはどのような理由なのでしょうか?
ある郷土学者は当時の大和朝廷が、征服した東北の民を懐柔するために、心の拠り所となる寺社を積極的に建立したからではないかと推測しています。大航海時代に西洋諸国がアジア諸国にキリスト教を普及させた後、植民地化していったのと同じような手段です。
そして寺社の建立とともに中央の人間を東北に移住させ、さらに神格化させた田村麿を東北の民に語り継いでいったというのです。田村麿自身すぐれた武将であったと共に神仏を厚く信仰する人徳者だったので東北の民も比較的容易に受け入れたのでしょう。こうしていつしか大和朝廷が建てた数々の寺社が田村麿が建てたということになり、言い伝えも数多く生まれたというわけです。以上のお話はあくまでも仮設ですが、ひょっとしたらねぶたまつりは坂上田村麻呂を神格化していく仮定で生まれた偶然の産物なのかもしれません。
注:坂上田村麻呂が東北に遠征する150年ほど前の650年代に、安陪比羅夫という朝廷の武将が日本海を船で北上し蝦夷地(北海道)まで遠征し蝦夷を征伐しています(公式の歴史書である日本書紀には北海道の北にある樺太まで遠征したと記されているが、事実かどうかは確認されていません)。坂上田村麻呂伝説は一説にはこの安陪比羅夫がモチーフとなっているのではないかとも言われています。
| 青森市のおすすめスポット情報 | ||||||
 |
青森市の観光・宿 |  |
||||
| 三内丸山遺跡 | 八甲田 | 八甲田丸 | 棟方志功記念館 | アスパム | ||
| モヤヒルズ | エーファクトリー | ねぶたの家 ワ・ラッセ | 浅虫温泉 湯の島 | 浅虫水族館 | ||
| 浅虫温泉 | 善知鳥神社 | 中世の館 | 合浦公園 | 青森の市場 | ||
| 青森ベイブリッジ | ねぶた祭り | 青森県立郷土館 | フェリー | |||